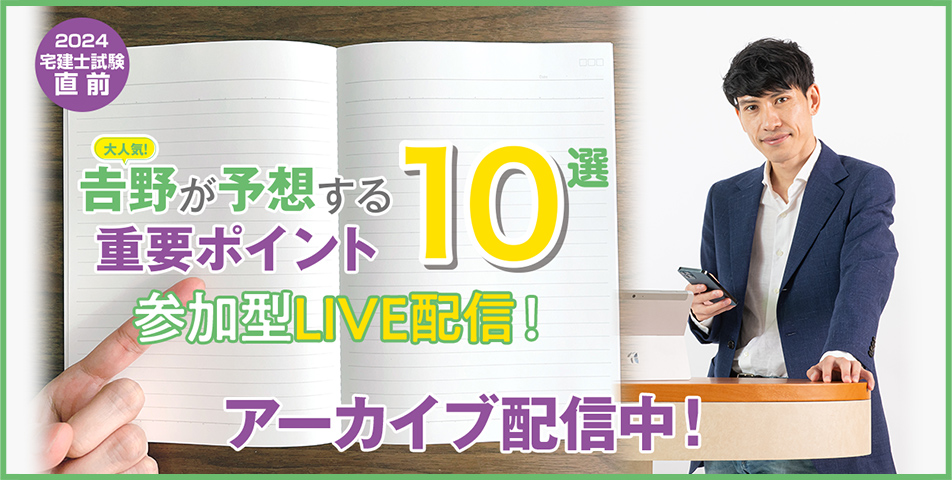皆さまのWEB採点が正確な
[合格推定点]算出に繋がります!!
今年も!どこよりも早く[合格推定点]を発表します!!
毎年、多くの受験生に好評をいただいている【日建学院の宅建本試験解答速報】。今年もリアルタイムで本試験データを分析し、いち早く!どこよりも早く!全問の解答と合格推定点を発表いたします!問〇で受験生の多くが選択した選択肢は何だったのか、みんなの選択肢が割れたのは問〇だったなどの考察も配信!宅建本試験後は日建学院の宅建解答速報にご期待ください!!
2024年度(令和6年度) 宅地建物取引士 本試験 解答速報
合格推定点 37・38点
- ※正解番号・合格推定点は、当学院が独自に判定したものですので、事前の予告なく変更になる場合があります。
- ※お問い合わせ:日建学院コールセンター[フリーコール] 0120-243-229/[E-mail] nikken@to.ksknet.co.jp
WEB採点サービス
宅建本試験
実際の試験で解答した番号と必要事項を入力してください。
当学院ホームページで「即日WEB採点」し、採点結果をメールにてお知らせします。
ご利用期間
2024年10月20日(日) 15:00頃~
2024年10月21日(月) 11:59まで
WEB採点サービスは終了しました
総評
総評
今年度の宅建試験について、全体的な難易度は、昨年の試験と同様にやや易しかったといえる。
権利関係は、昨年の試験と比較して、難易度は同程度でやや難しかったといえる。
昨年出題された個数問題は、今年も1問出題された。
毎年1問出題されている、判決文問題という特徴のある形式の問題が、今年は出題されなかった。
これに対して、条文規定問題が久しぶりに出題されたことは大きなトピックといえる。
今年の改正の目玉である問14『不動産登記法』については、今年の改正点は出題されなかったが、昨年の改正点が出題された。
昨年の改正という点では、問3『共有』で昨年の改正点について出題があった。
いわゆるマイナー項目からは、問6『混同』、問7『占有権』、問9『債務引受』から、合計3問も出題があった。
マイナー項目の出題が多かった影響からか、『代理』『物権変動』『不法行為』など、重要項目ではあるが、肢レベルでの出題に留まった項目が今年も多かった。
また、例年単独1問の出題のある『相続』については、今年は単独1問での出題がなかった。
特別法の問11~14については、比較的解きやすい問題が出題されたので、ここで得点を稼ぎたかったところだ。
全体として解きづらい問題も一部出題されたが、得点できる問題も出題されたといえる。
法令上の制限は、昨年の試験と比較して、難易度は標準的だったといえる。
改正の影響で、出題があるかどうか注目を集めた『宅地造成及び特定盛土等規制法』については、予想通り、単独1問の出題がなされた。
昨年、単独で出題があった『国土利用計画法』については、7年連続で単独の出題がなされたが、事前届出が久しぶりに問われたこともあり、解きづらい問題だったといえる。
問18『建築基準法』も解きづらい問題が出題された。
もっとも、問15『都市計画の内容』、問16『開発許可の要否』は、過去問で繰り返し問われているポイントが多く出題されたので、こちらは解きやすい問題だった。
税・価格の評定は、昨年の試験と比較して、難易度はやや易しかったといえる。
地方税では、大方の予想を裏切って『不動産取得税』が出題されたが、解きやすい内容が出題された。
また、国税は、『住宅ローン控除』が18年ぶりに出題されたことは、大きなサプライズといえる。
価格の評定については、こちらもあまり予想されていなかった『不動産の鑑定評価』が出題されたが、得点が期待できる問題であった。
宅建業法は、昨年の試験と比較して、難易度は同程度でやや易しかったといえる。
昨年の試験で7問出題された個数問題は、今年は3問と出題が減った。また、組合せ問題は2問出題された。
昨年、2問の出題に留まった『重要事項説明』は、今年は3問出題された。また、『37条書面』からも3問出題された。
『重要事項説明』『37条書面』を含むいわゆる『3大書面』から7問も出題されたことは大きな特徴であった。
もっとも、出題が予想された重要事項説明の改正点については、直接の出題はなかった。
昨年、多く出題された電磁的方法のポイントについては、今年も問35で出題された。
昨年に引き続き『クーリングオフ』と『手付金等の保全措置』は、単独1問出題がなされた。
問42では、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について、出題があったことが大きな特徴だった。
5問免除科目は、昨年の試験と比較して、難易度は同程度でやや易しかったといえる。
『住宅金融支援機構』『景品表示法』『統計』をはじめ、確実に得点できる問題が多く出題された。
全体的な難易度は、昨年と同様でやや易しかったといえる。
法改正などの情報を集めた上で、過去問を中心とした学習をしっかりとしてきた受験生であれば、解答できる問題が多かったといえる。
 本試験問題・解答解説集プレゼント
本試験問題・解答解説集プレゼント
無料ご希望の方全員に無料プレゼント!
2024年度(令和6年度)の宅建士本試験全50問の問題・解答解説はもちろんのこと、総評や正答率一覧などが掲載された試験データ満載の冊子です。
ご希望の方全員に無料プレゼント!下記のお申込みボタンよりお申し込みください。
※画像は昨年度のものです。

宅建合格後、取引士証交付までの流れ
必要な手続き
合格後、宅地建物取引士になるには、宅建登録と取引士証の交付を受ける必要があります。実務経験の年数によって、取引士証交付までの経過が違います。手続きを忘れずに行いましょう。
-
宅建本試験
合格 -
実務経験2年未満
実務講習の受講必要
実務経験2年以上
実務講習の受講不要
-
宅地建物取引士
登録 -
宅地建物取引士証
交付
※合格後、1年以上経過している場合、取引士証の交付を受けるためには、さらに法定講習の受講も必要となります。
実務経験がなくても取引士資格登録ができる「宅建実務講習」
2年以上の実務経験がなくても、宅建実務講習を修了すると、取引士資格登録ができます。
日建学院では全国47都道府県の会場で、宅建実務講習を実施しています。
日建学院の宅建実務講習
- Point1 便利!全国47都道府県に
会場があります! - Point2 早い!1月コース修了証は
2月初旬に発送されます! - Point3 信頼!約72,000名が受講。
安心の実績
充実の講義内容!
(2007年~2024年実績) - Point4 安心!インターネット限定!
早期申込&無料キャンセル
特約があります!
宅建実務講習の流れ
-
1. お申込み
ホームページからお申込みいただけます。下記「宅建実務講習 詳細・お申込み」ボタンよりご案内ページへお進みください。
-
2. 通信講座
テキスト、Web講義、自宅学習用問題を使用して、自宅学習を行ってください。
-
3. スクーリング(講習)
会場にて、2日間の演習を実施します。
-
4. 修了試験
修了試験は、90分の制限時間内で、4肢択一式20問の「択一式」と記述式20問の「記述式」を実施します。
-
5. 修了証交付
修了試験において、択一式、記述式それぞれいずれも8割以上の得点をされた方に対して、「登録実務講習修了証」を交付いたします。
宅建実務講習は定員制です。満席になり次第、受付を終了します。
お気軽にご相談ください
日建学院コールセンター
0120-243-229
受付時間 10:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)